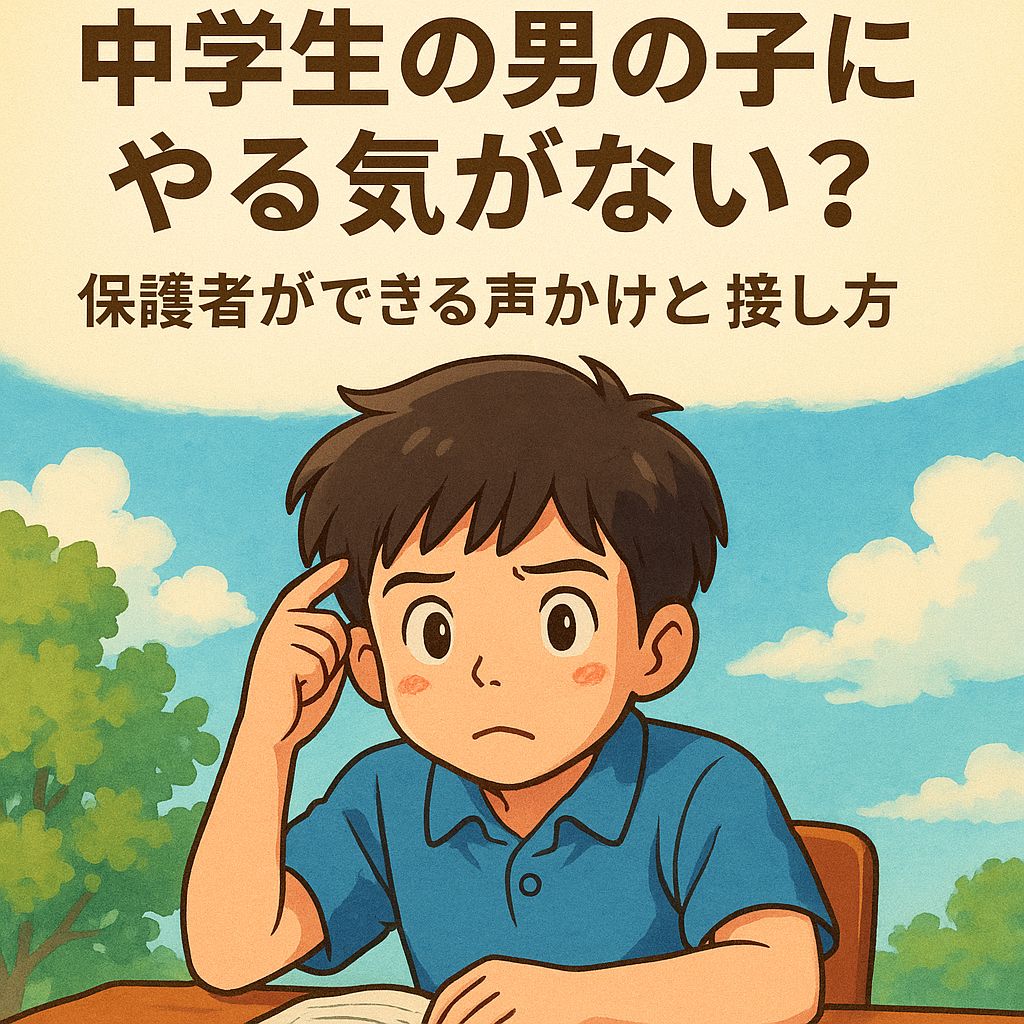
男の子の“やる気”が見えにくい
もちろん、すべての子に当てはまるわけではありません。ただ、これまで多くの子どもたちと接してきた中で、男の子に多いと感じる傾向があります。
それは、「勉強に対する熱量が低い」こと。
言われたことはやるけれど、嬉しさや悔しさがあまり表に出ない。
まるで、自分の勉強なのに他人事のように見えることもあります。
声をかけても反応が薄い…そんな姿に戸惑うことも
私自身、「どうしたら目的意識を持ってくれるだろう?」「どんな言葉が響くだろう?」と考えながら声をかけるのですが、なかなか手応えがないこともあります。
そんな子どもが、以前より増えてきているように感じるのです。
女の子はたくましい?現実的?
女の子は、全体的にたくましく、現実的。
「コツコツやって、希望の高校に行きたい」「将来は●●になりたい」
そんな目標に向けて自分をコントロールできる子が、男の子より多い印象です。
もちろん一概には言えませんが、こうした違いはたびたび感じます。
「熱」を持ってほしい。だからこそ向き合い続ける
子どもたちには、
「やりたい」「なりたい」
「くやしい」「次こそは!」
…そんな「感情のこもった“熱”」を持ってほしいと思っています。
とくに男の子たちに、どうしたらその火をつけられるのか。
教室でも、日々試行錯誤の連続です。
正解はない。でも、できることはある
子どもたちの気質や時代の変化を読み取りながら、
一人ひとりの性格を見極めて、丁寧に声をかけていく。
それを日々積み重ねていくことが大切だと感じます。
塾でさえも手探りなのですから、ご家庭での関わりは、もっとご苦労が多いことと思います。
ご家庭への一つのご提案:「自分で決めさせる」
失敗してもいいんです。
だからこそ、自分で決める経験をたくさんさせてあげてください。
「できること」ばかりをやっていては、そもそも失敗は起こりません。
でも、「失敗」は、自分の限界を越えようとした証拠です。
叱るより、「問いかけ」を
失敗したときは、叱るのではなく
「なぜそうなったんだろう?」
「どうしたらうまくいくと思う?」
と問いかけて、自分で考えさせてみてください。
そこから、「じゃあ、次はこうしてみよう」と
やり方を変える力=生きる力が育っていきます。
主体性は、早い段階で育てたい「生きる力」
大人はつい、先回りして正解を教えてしまいがちです。
でもそれでは、子どもが自分で考える機会を奪ってしまいます。
「魚を与えるのではなく、魚の釣り方を教える」
この言葉の通り、“自分で考える力”を育てることが大切なのです。
答えを与えず、問いかける
「エサは?」「場所は?」「どうやったら釣れる?」
そんな問いに、試行錯誤しながら自分なりに答えを見つける過程が必要です。
周りの大人が、“答え”ではなく“問い”を与えること。
それが、子どもたちの考えるクセを育てる第一歩になります。
根気よく、見守ることの大切さ
言うは易し、行うは難し。
私も教室で子どもたちを見ながら、もどかしさを感じることがよくあります。
でも、焦らず、根気よく。
きっと少しずつ、子どもたちの心に火が灯っていくと信じて、今日もまた岩見沢の子どもたちと向き合っています。